なぜこんなことを堂々と言えるのか?考えてみたことすらない方々にとっては、発想点すら新鮮だと思うのですよね・・・。
日本語は、共通理解や文化的常識シェアを強くプッシュすることを基として、
- 共感能力
- 洞察力
が自然と培われていきます。
かたや
英語は、たくさんの違った考え方ややり方、感情や常識のばらつきを基にして、
- 多様性
- 細分類化
- 論理性
- 言質
を求められて、それを表現する言語です。
ということは、この時点ですでに、英訳が上手になっても意味がないということですし、英語を日本語訳するときにその内容についての理解がないままであれば、非常に難しいということなのですよね。ズレが生じてしまう・・・。けれども多くの日本の英語教育は、この訳す行為のプロセスを最速化することを目標としている感が否めません。それでは、キリがない勝負に出ているし、いつまで経っても英語学習は続けねばならぬ感じになってしまいませんか?
時間がものすごくかかるので、他のことができなくなる可能性はあるし、ニュアンスや正確さや文化の違いなどもわからぬままで進んでいってしまいます。間違いを是とし続けて、それを励行することを促進するこの風潮は、ますます日本人に英語が話せない状態の継続を強いていくことでしょう・・・。(・・;)
それでもまったくかまわないのか、ニッポン!?と問いかけたいところです。
理解し合えない状態が続くということは、利点はほぼナシで、害ばかりが生まれます。
それが証拠に、日本はお金を生むことに長けているという認知はあるに拘わらず、G7などでも意見をとても尊重してもらえているか?というと疑問が残る・・・。安保があるからそれに従っていさえすればいいよ、という態度が垣間見られることもあったり、世界の中での立ち位置は、純然たる互いの理解から来ているのではなく、これまでの歴史的因縁や原因、パワーゲームに大いに影響されている気がしてなりません。
共感能力や洞察力が高いというスキルを、日本語を日々使っていることから自然と得られてしまう日本人は、言葉を尽くしません。なぜならば、「察してもらえる」「気持ちを汲んでもらえる」という期待値が高いからです。ですから、余計なことはなるべく言わないで、相手の裁量内で、不愉快を互いに感じないように受け止めて解釈してもらえればよい、というのが、日常的な期待値になります。
そういう日本語を、そうした文化がない英語圏の人々に単に英訳しただけでいいのか?という、端的な疑問を感じたことがないまま、英語学習をしていていいのだろうか?
英語は、イギリス人がヨーロッパに住み暮らしている頃から、廻りの国との国境のそばを体験していたり、跨いで行き来している経験があったことから、どんどんと「多様性」が進みます。そのため、同じことを前提とせず、「みんな違う」「同じように見えても微妙に違いがある」ということをきっちり説明せねばならぬ場面に、けっこうな機会遭遇してきます。
必要とあれば、しっかり表現せねば理解し合えないということがわかっており、言葉を尽くすようにする場面を弁えるようになったり、日常的に数をいちいち数えたり、形容詞や副詞でけっこう派手に物事を描写したりと、どんどん定着してきました。言葉をできる限り尽くすことが前提になります。
この真逆なものを、訳すだけの作業では、英語はできるようにはならない・・・。
そろそろ学習方法を変えていきませんか??





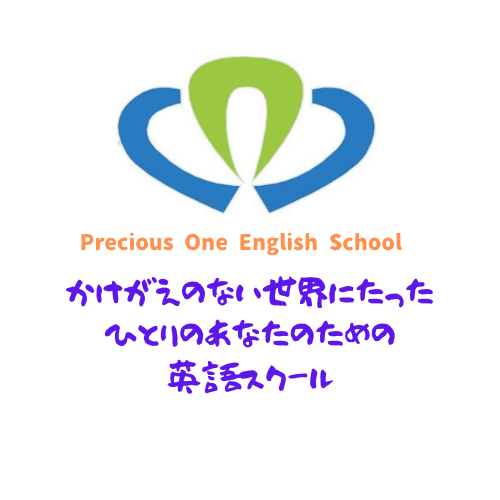













コメントを投稿するにはログインしてください。