日本語をそのまま英語に訳している作業の傾向が強い方には、para-phrasingを推奨しています。
Para-phrasing: express the meaning of (something written or spoken) using different words, especially to achieve greater clarity.
さらに意味を明確にするために、(書かれたり話したりされたもの)の意味を異なる言葉を使って表現すること。
なぜならば、何度かコラムでは書いてきましたが、文化や表現したいものが違うので、日本語をそのまま英訳しても、かなり意味がズレていることが多いのです。ですので、英語が話せるという定義すら、ブレていることも多く、単に英語化マシーンができてしまっている気がしないでもない、日本の英語教育ではあります。
英語のコミュニケーションの目的は、
理解を獲得すること
かっこいいよね(笑)。なので、聞き手や読み手が、自分の判断を「正しい」とひとりごちることはNG。わからない場合はちゃんと質問するのが日常だし、話し手や書き手も、相手がわかるように表現することがそもそものコミュニケーションの使命なのです。
そうした意味では、日本人が日本語をそのまま英語に訳すと、かなりチンプンカンプンなものが多い。その大半は、日本語のHigh context:広い範囲を指すように表現し、そうした単語を好む、という傾向から来ています。
昨今もプライベートレッスンをしたあと、生徒さんが、「調子が悪い」とは英語ではどう表現したらいいか?という質問があり、1時間のレッスンは一体何だったのだろう?と、少し脱力しました(笑)。だって、調子が悪いことの範囲を狭めていないし、身体なのか心なのか両方なのかも方向性を示さないし、自分で原因のアテがついているのかまったくわからないのかも示唆できていないし、いつもと同じようなだるさとか調子の悪さなのか、まったく初体験なのか、など、そうしたことにも言及することがやたらと多いのです、英語は。
そこを表現しない英語は「相手をテキトーに扱っている」か、「相手が日本人レベルで察してくれたり、共感してくれるから言わずもがな、ができてしまう」という場合のみ。
理解をしてもらうために、自分のほうがしっかり折れて表現を最大限工夫してみるクセをつけないと、日本人には英語はマスターする方向には向かないのです。だって、日本人は、プロじゃない限り、何を食べても、「おいしいーまずい」の二元で、まぁ、ちょっとマシだと、「おいしいーふつうーまずい」になるくらいで、だいたいの方向性を広く取って生活していることに、自分たちでも気づけていないのですから。
せっかくの英語学習です。気づきを体現できるようにしていただけたら、ますます楽しくなると思うんですよ(^^♪







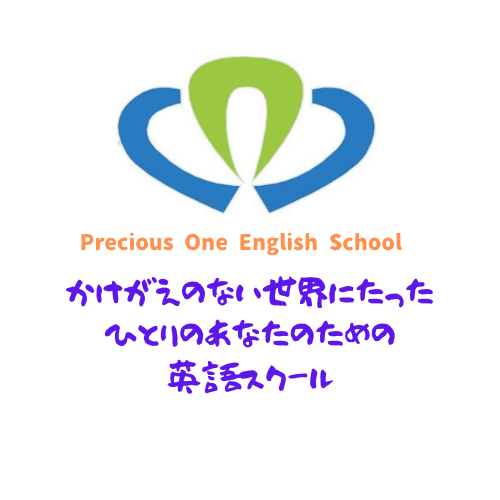














コメントを投稿するにはログインしてください。